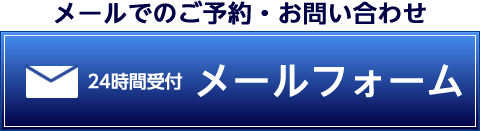相続・遺言
相続に強い弁護士が遺産分割のご相談から交渉・調停・審判までフルサポート。
遺産分割事件の実績多数。
全国の裁判所に対応可能。
地元密着のため、不動産分野に強い。
当事務所は、2013年に岡山県岡山市で開業以来、相続・遺産分割事件の取り扱い数が豊富な法律事務所です。
おかげさまで多くの相続・遺産分割事件のお問い合わせを頂いてきましたが、その中でも最近は「他県に住んでいるものの、相続対象の不動産が岡山県内にあるため、岡山の弁護士にお願いしたい」というお客様からのご依頼も頂いております。岡山県外にお住まいのお客様でも、初回相談のみは来所をお願いしておりますが、ご依頼後はオンライン相談を取り入れるなど柔軟に対応いたしております。
遺産分割後の相続税申請や不動産登記が必要な事件につきましては、税理士・司法書士と連携して、地元密着ならではのワンストップサービスをご提供いたします。また、顧問弁護士業務を長く手掛けてきたことから、会社経営等の複雑な相続事案にも対応が可能です。
税務や登記、会社関係などが絡み合った複雑なケースでも、相続・遺産分割の問題でお悩みの方は、どうぞお気軽にご相談ください。
中村英男法律事務所
代表弁護士 中 村 英 男

・兄弟から突然遺産分割の調停を申し立てられた
・相続人の一人が法定相続分を越える理不尽な遺産の取り分を主張してきた
・兄は父の生前に家を建ててもらったのに、相続財産を平等に分割しようと言ってきた
・ 亡くなった親の介護をしてきたので、寄与分を主張したい
・相続財産の中に金銭だけでなく、アパートなどの収益物件・不動産が含まれている
・ 亡くなった父が所有していた土地の固定資産税を立替払いしているので、他の兄弟にも請求したい
・亡くなった父が事業をやっていたため、株式や貸付金など権利関係が複雑になっている
・相手方が遠方に住んでいるため、話し合いがスムーズにいかない
・遺留分を請求したい
弁護士が最適な解決策をご提案

ご家族が亡くなられた場合、亡くなられた方の遺産の分割について、兄弟など親族の間で争いになるケースは少なくありません。
特に、相続問題においては、特別受益(生前贈与)や寄与分、遺留分、遺産の使い込み、遺言書の無効を争うといった特別な事情がある場合や相続財産に不動産が含まれている場合、会社経営をされていた場合など、当事者のみの話し合いで解決するのが難しく当事務所にご相談に来られるケースが多くあります。
また、金銭的問題だけではなく、兄弟などの親族間での争いごとになることから、当事者のみで交渉や調停を続けることで、相当な精神的負担が発生するため、交渉や調停・裁判を依頼されることもあります。
当事者同士の話し合いでの遺産分割がうまくいかない場合には、相続問題を熟知した弁護士に交渉や調停を任せることで、冷静な話し合いが可能になり、遺産分割手続を解決に導くことができます。
さらには当事務所にご依頼いただいた場合、預貯金の不正な引出しを弁護士会を通じて調査したり、地元の不動産会社を通じて適正な不動産価格を調査したりすることが可能です。
中村英男法律事務所は、遺産相続分野で数多くの実績を誇り、不動産分野・顧問弁護士業務にも精通した弁護士が相手方との交渉や遺産分割調停など、最適な解決策をご提案いたします。
弁護士が遺産分割交渉・調停・審判までフルサポート
相手方が遠方に住んでいる場合や、相続財産の中にアパートなどの収益物件・不動産が含まれている場合、生前贈与や寄与分、遺留分が争いとなっているケースなどでは、話し合いがスムーズにいかないことが多くあります。弁護士に交渉を任せたり、調停を申し立てたりする解決方法があります。
遺産分割協議書にサインする前に一度弁護士にご相談を
被相続人の死亡後、弁護士や司法書士・税理士などから「遺産分割協議書」が送られてきて、署名・捺印を求められることがよくあります。
遺産分割協議書に一度署名・押印をしてしまうと、原則的には取り消すことはできませんので、協議書が届いた場合には、まずは一度弁護士にご相談ください。
相続財産に不審な点がある場合は遺産の調査が可能
被相続人が生前に認知症を患っていたり、施設に入院していたりした場合に、相続人の一人が財産を管理しているケースがあります。他の相続人が被相続人の預貯金を生前に使い込んでいたのではないか疑いをお持ちの場合には、弁護士が被相続人が亡くなる前の預貯金の出入金の記録を照会して、調査することが可能です。
相続財産・相続関係に疑問や不審な点がございましたら、交渉や調停などの事件をご依頼頂いた場合には、遺産分割事件解決のために必要な範囲で、預貯金の使い込みの調査や戸籍などを取り寄せる相続関係の調査などを行うことが可能です。
ご解決事例
※守秘義務の観点から、事例は実際に取り扱った事案を一部改変してあります。
【Case1】遺産分割調停を申し立て、相続分が2500万円増額した事例
相続財産:預貯金、株式、アパートなどの収益物件、不動産等
亡くなられた方:父 相続人:子2人
お父様が亡くなられた後、お父様と同居していたお姉様から遺産分割協議書案が突然送られてきたものの、ご自身の取り分が不当に低く抑えられていることに到底納得がいかなかったため、弁護士に調停申立をご依頼くださいました。
調停を申し立てる前に、まずは、お姉様がお父様の預貯金を生前に勝手に引き出していなかったかどうかを弁護士会を通じて各金融機関に調査を依頼し、また、アパートや不動産の査定を依頼することにより、正確な相続財産を調査いたしました。
その後、裁判所に調停を申し立てたところ、相手方が不動産の価値を不当に低く見積もっていることや預貯金を使い込んでいたことを主張することにより、当初の分割案よりも多く相続する内容の調停が成立しました。
|
当初分割案 |
弁護士依頼後 |
取得分 |
|
5000万円 |
→ | 7500万円 |
【ポイント】相続財産が多額であり、かつ預貯金の他にアパートなどの収益物件や不動産など多くの相続財産があったため、調停申立前に預貯金や不動産の調査をすることにより、調停の中でこちらの主張が多く認められ、結果的に当初の分割案よりも2500万円も多くの相続財産を受け取ることができました。
【Case2】遺留分減殺請求後、調停を申し立て、1名当たり1000万円以上の支払いが認められた事例
相続財産:不動産、預貯金等
亡くなられた方:父 相続人:子3人
お父様が亡くなられた後、兄弟の1人に全財産を相続させる旨の公正証書遺言が存在することが判明し、兄弟間での協議が難航したことから、相続人であるご兄弟お2人から弁護士にご相談、ご依頼いただきました。
遺留分減殺請求後、相手方に弁護士が就任し、弁護士間で協議しても時間を要することが予想されたため、調停を申し立てました。
調停申立後、調停委員からの説得もあり、相手方が相続した不動産の一部を売却して、その代金を申立人らに対する支払いに充てるという内容で調停が成立し、無事支払いを受けることができました。
|
遺留分減殺請求前 |
弁護士依頼後 |
取得分(1人当たり) |
|
0円 |
→ | 1000万円以上 |
【ポイント】相続財産のうち、不動産が多数存在し、その評価が問題になったところ、不動産業者の査定を取得し、時価での算定評価を主張することにより、より多額の遺留分を認めてもらうことができました。
【Case3】遺産分割交渉により、不動産共有持分および預貯金の約2分の1を取得する内容で解決に至った事例
相続財産:不動産、預貯金等
亡くなられた方:母
お母さまが亡くなられた後、不動産共有持分の分割方法、租税等の負担方法について協議がととのわないため、ご相談、ご依頼いただきました。
交渉により、不動産共有持分は当方で取得すること、租税・立替金等については代償金により調整することなどを取り決め、遺産分割協議書作成後、分割、相続税の申告が無事完了しました。
|
当初 |
弁護士依頼後 |
取得分 |
|
|
→ |
不動産共有持分 約500万円 + 預貯金 約2100万円 |
【ポイント】不動産共有持分について、どちらが取得するかや未登記建物の処理等様々な問題がありましたが、1つ1つ丁寧に交渉したことが解決につながったと思われます。
相続税の課税対象の方へ
平成25年税制改正により、基礎控除額が従前より4割引き下げられることになり、今までなら相続税がかからなかった方でも相続税の課税対象になるケースが大幅に増加し、当事務所にご相談に来られるお客様も対象となられる方が増加しております。
相続税の課税対象になられる方の多くが、相続財産の中に、現金や預貯金、不動産、アパートなどの収益物件、株式などを含んでおり、遺産が複数かつ高額になるケースが多いため、遺産分割の際に当事者間での話し合いでの分割が難しいことがあります。当事者の話し合いの際、遺産分割の内容に納得がいかない場合には、遺産分割協議書にサインをする前に、一度弁護士にご相談されることをお勧めします。
当事務所では、遺産分割協議書の作成も承っております。当事者間で遺産分割の話し合いができている場合につきましては、協議書の作成のみを弁護士に依頼することも可能です。お気軽にお問い合わせください。
遺産を遺す方へ ~遺言書の作成をお勧めいたします~
遺産を残す方は、元気なうちに、誰に、どの遺産を、どれだけ相続させるかについて遺言書を作成しておくことも、遺産分割での争いを避けるためには重要なことであると考えております。 当事務所では、遺言書作成や遺言執行、成年後見の申立てなどのご依頼も承っておりますので、お気軽にご相談ください。
相談の際にご持参頂きたい資料
2.遺産目録(簡単なメモでも結構です。)
3.遺言書のコピー(遺言書がある場合)など

上記の資料がお手元にございましたら、ご相談時にご持参ください。資料がない場合には、お持ちいただかなくても、ご相談をお受けしています。
ご相談予約
- 弁護士へのご相談をご希望の方は、まずはお電話( TEL 086-206-6801)でご予約ください。
- 電話予約の受付時間は平日9時から17時までとなっております。
- メールでのご予約も承っております。
- 夜間・土日のご相談については、電話受付時間内(平日9時~17時)にお問合せください。
- 難しい専門用語を使わず、わかりやすくご説明いたします。
- 初めての方でもお気軽にご相談ください。
事務所のご案内
所在地
〒700-0816 岡山県岡山市北区富田町二丁目12番16号 センチュリー富田町101号
岡山駅から徒歩10分 /駐車場完備
Copyright©2013nakamurah. All Rights Reserved.